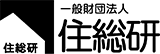平成22年度(2010年度)より、研究・実践活動の効率化と成果の集約化を図るため、各年度に取り組むべき重点テーマを定め、その年度に開催されるシンポジウムをはじめ、研究・実践助成の選定及び諸活動に反映しております。
2027年度重点テーマ
「住まいの不易流行」
大橋 竜太(東京家政学院大学 教授)
人びとの生活の場である住まいは、社会の変化とともに日々変容してきた。生活の発展といった観点からは、それに対応した住まいの変化は当然のことであろう。一方で、社会や人びとの生活が変化しても変わらぬものもある。それが住まいの伝統であり、生活文化であろう。すなわち、住まいは「不易流行」を繰り返しながら発展してきた。他方、現代社会では、人びとの生活は多様化し、住まいにも多面性が求められている。こういった状況で、今一度、生活文化といった観点から、住まいにおける「日本らしさ」とは何かを考え直してみる必要があるのではないか。そのうえで、わが国の住まいの未来像を追求していきたい。
「日本らしさ」を追求するために、「住まいの変化」に注目したい。たとえば、明治時代以降の西洋文化が到来するとともに、わが国の住まいは大きく変化した。これは新たな生活習慣が導入されたことによる住まいの変化であるが、住まいやすさの追及や新技術の導入で変化したものもある。しかし、住まいが変化するといってもすべてが変化するわけではなく、変わらぬものもある。それがよく現れるのが、住まいの増改築時であろう。住まいの増改築では、新たに必要な空間が加えられ、不要なものは除かれるが、なかにはそのまま保たれる部分もある。変化しないものには、生業との関係からくるものもある。マタギの家や海女小屋は、一般の住宅とは異なり、社会の変化等の影響をほとんど受けずに、根本的構成は保たれている。住まいのなかで変わらぬものを探るには、プリミティヴな姿を追求するのもひとつの手法であろう。また、住まいの伝統は、年中行事や冠婚葬祭とともに残っている場合や上層階級の住宅で形成されたステータスが庶民住宅のなかで継承される場合もあり、外部空間を含めた地域のコミュニケーションのなかで継承されていることもある。住まいが多様化するなか、それらに影響を与えた要因やその結果としてのかたちを検討しながら、住まいの伝統を時代に合わせて新たに解釈していきたい。
わが国の将来の住まい像を考える際、高齢化社会や持続可能な社会など、取り組んでいかなければならないことは多数ある。一方で、個人や生活の共同体である家族、社会といった広い観点から、日本人にとっての住まいの伝統を見つめ直し、新しくしていくものと守っていくものを明確にする必要があるだろう。つまり、「住まいの不易流行」をあらためて考えることが、未来の住まい像の提案へとつながるはずである。以上を重点テーマとして設定したい。
研究テーマ設定のためのキーワード
- 生活様式
- 住まいやすさ
- 技術
- 増改築
- 生業
- プリミティヴな住まい
- 年中行事・冠婚葬祭
- ステータス
- 外部空間
- コミュニケーション
- 伝統の解釈
「住まいの不易流行」研究委員会
(委員五十音順)2025.10月現在
- 大橋 竜太
- (東京家政学院大学 教授)
- 大井 隆弘
- (三重大学大学院 准教授)
- 小柏 典華
- (芝浦工業大学 准教授)
- 永井 康雄
- (山形大学 教授)
- 中村 駿介
- (石川県金沢城調査研究所 主事)
- 山村 明子
- (東京家政学院大学 教授)
2026年度重点テーマ
「リジェネラティブ(再生成)なすまいとまちへ:持続可能性を超えて再編される住宅地と都市」
小泉 秀樹(東京大学大学院 教授)
気候変動への対応や生物多様性確保、高齢社会や少子化問題の対処と解消、移民の受け入れなど21世紀に入り、多様な課題に対し、並立的・調和的もしくは創造的対応を求められている現代の住宅地及び都市の再編の実態や目指すべき住宅地・都市像を探究することをテーマとしたい。
その際、リジェネラティブ(regenerative:再生成的(筆者による和訳))概念に着目する。リジェネラティブ(再生成)は、特に欧州においてこれからの住宅地や都市の更新のあり方を示すものとして注目されている計画概念である(参考文献参照)。
リジェネラティブ(再生成)概念は、持続可能性を超えて、環境に配慮した再生を果たすという観点から紹介されることが多いが、本研究課題ではその点を包含しつつ、以下の2点をさらに付加した(含意した)概念として提起したい。一つは、現在未来の課題に応答し得る生成的に変化を生み出すメカニズムを持つ(人やもの(人工物)自然的環境が一つの系として相互に関連しながら生成的再生をすること、そのプロセスを具備すること)という含意であり、今一つは、気候変動への対応や生物多様性確保、高齢社会や少子化への対処と解消、移民の受け入れなどを含む社会的包摂への対応などが複雑に関連しあった現代住宅地・都市の課題について、調和的かつ創造的に解決方法を見出す、という含意である。
こうしたリジェネラティブなすまいとまちへと転換するために何が課題であり、何が求められているのか?
例えば、各課題を個別に解決すると想定される住宅地や都市のあり方はどこまで(どのような方法で)明らかになっており、またそれはどのような姿や像であるのかについて整理した上で、それらに関する探究をさらに深める必要があろう。(つまりは、気候変動や生物多様性に対応した住宅地や都市、高齢社会や少子化に対応した住宅地や都市、社会的包摂を実現する住宅地や都市とはどのようなものか、その像やその探究方法について検討し発展させる必要があるだろう)
その上で、カーボン及びネイチャーポジティブでありながら社会的包摂や高齢/少子化社会といった多種の課題に対応し得るリジェネラティブ住宅地・都市とはどのような形態であるのか、更にはどのように生成的に生み出されるものなのか(像や、生成方法メカニズム・実現に必要とされる社会制度や主体論、プロセス論など)について探究する必要があろう。そして、これらの点を探るために内外の先進的な事例に学ぶことも有効であるかもしれない。
持続可能性を超えて再編されるリジェネラティブな住宅地と都市のあり方を探究する意欲的な研究と実践を期待します。
研究テーマ設定のためのキーワード
- リジェネラティブ
- 気候変動・生物多様性への対応
- 社会的包摂
- 少子化、高齢化社会への対応
- 場所論
- スマートシティ
「リジェネラティブ(再生成)なすまいとまちへ」研究委員会
(委員五十音順)2024.10月現在
- 小泉 秀樹
- (東京大学大学院 教授)
- 中島 弘貴
- (東京大学大学院 特任講師)
- 西村 愛
- (明海大学 准教授)
- 三浦 詩乃
- (中央大学 准教授)
- 宮森 剛
- (国土交通省 住宅局)
- 村山 顕人
- (東京大学大学院 教授)
2025年度重点テーマ
「ネットワーク化する住み方と住まいのかたち」
小伊藤 亜希子(大阪公立大学大学院 教授)
人口減少時代に入り、家族の形も縮小するとともに多様化しています。単身や夫婦のみ世帯の数は半数を超え、またひとり親世帯、世帯内単身者、非血縁家族など家族のかたちも多様になり、子育て核家族である「標準家族」はすでに標準ではなくなりました。戦後にモデルチェンジし、プロトタイプとして大量に供給されたnLDK 型住宅ストックは、その使われ方の変容を迫られています。
一方、縮小した家族は、必然的につながりを求めることになります。子育てや高齢者ケアを家族ネットワークで支え合う親子近居はその典型です。またこれからの時代は、シェア居住や住まいを開くことによって、血縁を超えてつながりをつくる住み方も重要性を増していくものと思われます。
一住宅一家族にとどまらず、そうした多様な家族と住み方を受け入れる住宅のかたちやしくみのあり方が問われています。
そこで課題になるのが、どこに住むのかの選択です。コロナ禍を契機とした在宅ワークの普及は、居住地選択の幅を広げました。勤務地との距離よりも住宅やライフスタイルを優先する人が現れ、地方移住も注目を集めるようになっています。Uターン移住による近居や多拠点居住、転職や起業による働き方の変化も含め、移住はライフスタイルの大きな変化を伴います。また関係人口とよばれる地域に強いつながりをもつ人々の存在も注目されます。多様な人口を受け入れ、ネットワーク化する新しい住み方に対応する住宅や場をどう供給するのかは、空き家ストックの活用を含め、高齢化・人口減少の課題を抱える地域としても大きな課題です。働く場を兼ねた住宅、小さな家族や家族を超えた居住を受け入れる住空間は、機能分離を主眼とする nLDK 型では収まりきらず、日本の伝統住宅が持っていた柔軟な空間特性への回帰、再評価も課題になるでしょう。
さらに移住や海外にルーツをもつ多様な人々が、新しい居住地や住宅にどのように馴染み、働き方、住まい、地域の人とのつながりを含め、段階的にライフスタイルをカスタマイズしてゆくプロセスとその支援も重要です。
こうしたネットワーク化する住み方に対応し、家族やコミュニティのダイバーシティと多様なライフスタイルを許容し、だれもが豊かに暮らせる住まいのかたちとしくみづくりに寄与する研究と実践を期待します。
研究テーマ設定のためのキーワード
- 家族縮小
- 家族のダイバーシティ
- 近居
- 移住
- 多拠点居住
- シェア居住
- 開かれた住まい
- 脱nLDK
- 住宅ストック活用
「つながりをつくる新しい住まいのかたち」研究委員会
(委員五十音順)2023.7月現在
- 小伊藤 亜希子
- (大阪公立大学大学院 教授)
- 川田 菜穂子
- (大分大学 准教授)
- 葛西 リサ
- (追手門学院大学 准教授)
- 近藤 民代
- (神戸大学 教授)
- 土井 脩史
- (大阪公立大学大学院 講師)
- 柳沢 究
- (京都大学大学院 准教授)