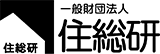2026年度
研究・実践助成 募集要項
住関連分野における研究の発展や研究者の育成及び支援の観点から、将来の「住生活の向上」に役立つ内容で、
学術的に質が高く、社会的要請の強い又は先見性や発展性等が期待できる「未発表」の「研究活動」に対して助成します。
募集要項
A-1.助成概要について
1.1
助成テーマ
「住生活の向上に寄与する住関連分野の研究」とし、他分野に及ぶ学術的な研究などを含み、未発表のものを助成します。
助成対象は、「重点テーマに係わる研究」、「自由なテーマでの研究」のいずれでも可とします。
「重点テーマ」とは、その年度の住総研の活動の焦点となるもので、本年度は次のとおりです。
| 重点テーマ | 住まいの不易流行 |
|---|---|
| 自由テーマ | 任意にテーマを設定 |
詳細については、以下A-4.「重点テーマ」・「要旨」・「キーワード」を参照してください。
1.2
助成対象
| 助成対象 | 「住生活の向上に寄与する住関連分野の研究」とし、他分野に及ぶ学術的な研究などを含み、「未発表」のものを助成します。 |
|---|---|
| 実践助成 | 「住生活の向上に寄与する住関連分野の実践研究活動」とし、学術的な研究を伴う試行中または運営中の実践活動に対して、「未発表」のものを助成します。実践活動とは、例えば、住宅建築計画、住環境関連などの分野、およびまちづくり活動、施設等での住まい方の試み等で、以下2.1の基準を満たし、その実践活動が、他の類似の活動にも「応用」・「水平展開」できる活動を指します。なお、学術的な研究とは、方法論として体系化され整理されている活動とします。 |
1.3
応募資格
- 当該研究のためのグループ(2名以上で構成:以下当該委員会と呼ぶ)とし、既存の団体・組織としての応募は出来ません。(各自の所属は問いません。応募グループは、複数の団体・組織・機関等にまたがっても構いません。) 当該委員会とは:1.5(5)参照。
- 英語での応募の場合は、日本語サマリー(申請書/A4版1枚程度)を追加で提出してください。但し、当財団の成果物は、原則、日本語で作成されたものを提出していただきます。英語での成果物を希望される場合は、個別に審議し決定いたします。
1.4
助成件数
研究助成及び実践助成あわせて25件程度
1.5
助成内容
| (1)金額 | 1件当り150万円を上限とします。 (但し、助成金額は申請額からの減額調整を行う場合があります。) |
|---|---|
| (2)費目 | 謝金/会議費/資料・印刷・複写費/交通費/出張旅費/機器・備品費・損料/雑費 |
| (3)期間 | 2026年7月1日~2027年10月末日までの16カ月間 |
| (4)提出物 | 中間時(2027年2月末日):「中間報告書(PDF形式)」及び「研究・活動計画書(PDF形式)」 完了時(2027年10月末日):「成果物(研究論文-版下原稿のPDF形式)」及び「会計報告書(システム入力)」 |
| (5)主な注意点 |
|
1.6
発刊・公開
提出された成果物は、選考委員会で査読し、内容を確認後、当財団発行の『住総研 研究論文集・実践研究報告集』に収録し、当財団HPやJ-STAGE等で公開します。
1.7
顕彰・発表・公開
提出された成果物の中から、毎年6編程度を採択し、「住総研 研究・実践選奨」及び「奨励賞」として表彰します。また表彰式後、記念講演会で発表していただき、当財団HPで、受賞者リストと記念講演会の動画等を公開します。
1.8
知的財産権等の取り扱い
以下の内容の許諾について予め、ご了承いただきます。
- 助成を受けた成果物の著作権は、著者に帰属するものとしますが、当財団が、助成の成果を公開する為に、必要な範囲で、『住総研 研究論文集・実践研究報告集』を複製・編集出版すること。
- 助成の成果として得られた工業所有権は発明者に帰属するものとしますが、当財団に対して、無償の通常実施権について許諾すること。
- 必要に応じて当財団に提出される個人情報については、当財団が、当財団の事業等の案内及び情報提供の範囲で、使用すること。
- 当該成果物に掲載された文章・写真・図版等で引用・転載されているものがある場合は、原作者からの許諾もしくは、論文中への許諾同等の表記を行うこと。
- 当該成果物に記載された個人情報については、当該委員会の責任において対処するものとし、当該委員会は別途「助成の個人情報取扱いに関する誓約書」を当財団に提出すること。
- その他、別途「助成 実施の手引き」に基づき、遵守する事項の誓約書「助成の受給及び成果物の取扱い等に関する誓約書」を当財団に提出すること。
A-2.選考について
2.1
基準
目的・課題の設定が明確で、研究として一定の水準に達すること、新たな知見が存在すること、が期待され、かつ以下の一つ以上の項目に該当すると判断されるものとします。
- 学術的に質の高い研究成果
- 公益性を有し、社会的要請が高い課題への取組み
- 先見性・独創性に富み、将来の発展性が期待できる課題への取組み
- 社会的な実用性の向上に貢献する事が期待できる取組み
- 将来の成長が期待できる若手研究者による取組み
2.2
選考方法
選考委員会(研究運営委員会)で選考し、理事会・評議員会を経て、決定します。
2.3
選考結果
提出された成果物は、選考委員会で査読し、内容を確認後、当財団発行の『住総研 研究論文集・実践研究報告集』に収録し、当財団HPやJ-STAGE等で公開します。
2.4
選考委員会
| 委員長 | 小伊藤 亜希子 (大阪公立大学大学院 生活科学研究科 教授) |
|---|---|
| 委員 | 大橋 竜太 (東京家政学院大学 現代生活学部 教授) |
| 委員 | 窪田 亜矢 (東北大学大学院 工学系研究科 教授) |
| 委員 | 小泉 秀樹 (東京大学大学院 都市工学科都市工学専攻 教授) |
| 委員 | 志手 一哉 (芝浦工業大学 建築学部 教授) |
| 委員 | 髙口 洋人 (早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 教授) |
A-3.応募について
3.1
応募期間
2025年10月1日(水)~2026年1月31日(日)
3.2
応募締切
2026年1月31日(日) 23:59データ送信分まで受付
3.3
応募方法
応募はWEB申請となります。「助成金受付システム」から、ログインIDとパスワードを登録後、申請画面に従って入力してご応募ください。申請書を受信後、「申請登録通知」(申請書受理通知)メールが自動送信されます。
※WEB申請の詳細につきましては別途「WEB申請マニュアル」をご覧ください。
3.4
注意点
- ID・パスワード使用上限数に伴い、過去に本申請システムで使用された「ID」と「パスワード」は、使用できませんので、ご注意ください。
- 24時間を過ぎても「申請登録通知」メールが届かない場合は、申請書が当財団宛に受信されていませんので、以下、研究・実践助成担当宛にお問い合わせの上、必ず申請登録を確認ください。
- 締切後の受付は、いたしかねます。締切間際の応募(データ送信)は、応募が集中し、データが送信されない場合があります。時間に余裕をもってご応募をお願いたします。
A-4.「重点テーマ」・「要旨」・「キーワード」について
4.1
重点テーマ
「住まいの不易流行」
4.2
要旨
人びとの生活の場である住まいは、社会の変化とともに日々変容してきた。生活の発展といった観点からは、それに対応した住まいの変化は当然のことであろう。一方で、社会や人びとの生活が変化しても変わらぬものもある。それが住まいの伝統であり、生活文化であろう。すなわち、住まいは「不易流行」を繰り返しながら発展してきた。他方、現代社会では、人びとの生活は多様化し、住まいにも多面性が求められている。こういった状況で、今一度、生活文化といった観点から、住まいにおける「日本らしさ」とは何かを考え直してみる必要があるのではないか。そのうえで、わが国の住まいの未来像を追求していきたい。
「日本らしさ」を追求するために、「住まいの変化」に注目したい。たとえば、明治時代以降の西洋文化が到来するとともに、わが国の住まいは大きく変化した。これは新たな生活習慣が導入されたことによる住まいの変化であるが、住まいやすさの追及や新技術の導入で変化したものもある。しかし、住まいが変化するといってもすべてが変化するわけではなく、変わらぬものもある。それがよく現れるのが、住まいの増改築時であろう。住まいの増改築では、新たに必要な空間が加えられ、不要なものは除かれるが、なかにはそのまま保たれる部分もある。変化しないものには、生業との関係からくるものもある。マタギの家や海女小屋は、一般の住宅とは異なり、社会の変化等の影響をほとんど受けずに、根本的構成は保たれている。住まいのなかで変わらぬものを探るには、プリミティヴな姿を追求するのもひとつの手法であろう。また、住まいの伝統は、年中行事や冠婚葬祭とともに残っている場合や上層階級の住宅で形成されたステータスが庶民住宅のなかで継承される場合もあり、外部空間を含めた地域のコミュニケーションのなかで継承されていることもある。住まいが多様化するなか、それらに影響を与えた要因やその結果としてのかたちを検討しながら、住まいの伝統を時代に合わせて新たに解釈していきたい。
わが国の将来の住まい像を考える際、高齢化社会や持続可能な社会など、取り組んでいかなければならないことは多数ある。一方で、個人や生活の共同体である家族、社会といった広い観点から、日本人にとっての住まいの伝統を見つめ直し、新しくしていくものと守っていくものを明確にする必要があるだろう。つまり、「住まいの不易流行」をあらためて考えることが、未来の住まい像の提案へとつながるはずである。以上を重点テーマとして設定したい。
4.3
キーワード(参考例)
生活様式
住まいやすさ
技術
増改築
生業
プリミティヴな住まい
年中行事・冠婚葬祭
ステータス
外部空間
コミュニケーション
伝統の解釈
A-5.今後のスケジュール
| 実施時期 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2025年 | 10月1日~ | 研究・実践助成 応募受付開始 |
| 2026年 | 1月31日〆切 | 研究・実践助成 応募受付終了 |
| 4月上旬 | 選考委員会による選考 | |
| 6月中旬 | 理事会・評議員会による採択決定 | |
| 6月下旬 | 選考結果通知(主査および主査代理人へメール) | |
| 7月1日~ | 助成活動開始 | |
| 7月25日頃 | 第1回 助成金交付(助成額の70%) | |
| 2027年 | 2月28日〆切 | 中間報告書、研究・活動計画書 提出 |
| 3月上旬 | 選考委員会による中間報告書査読 | |
| 5月中旬 | 中間報告に対する選考委員会からのコメント通知 | |
| 5月25日頃 | 第2回 助成金交付(助成額の30%) | |
| 10月31日〆切 | 成果物(研究論文)、会計報告書 提出 | |
| 2028年 | 5月25日頃 | 成果物の修正期間 |
| 3月下旬 | 『住総研 研究論文集・実践研究報告集』収録 | |
研究・実践助成に応募される方
住総研 助成金受付システム
お問い合わせ
一般財団法人 住総研
研究・実践助成担当
E-mail:
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルヂング2階
TEL:03-3275-3078
FAX:03-3275-3079