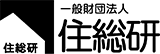2024年度重点テーマ
「郊外住宅地のネイバーフッドマネジメント」
齊藤 広子(横浜市立大学 教授)
重点テーマは、「郊外住宅地のネイバーフッドマネジメント」である。ここでいう、住宅地は、所有形態を問わず、戸建て住宅地、団地、集合住宅、マンション、そしてこれらが混在するものを指している。こうした住宅地では、再生の必要性が高まっている。住宅所有者自身は高齢化し、なかなか自らで再生することが難しい。また、行政も私有財産に手を出すことには課題がある。住宅地・住宅をつくった開発事業者は、「手離れ良く」その場から去っている。そこで、なんとか、地元町内会や自治会での対応もあるが課題が多い。そのなかで、町内会をベースにした NPO、一般社団法人、民間企業などによる再生事例も見られている。今後、補助金に依存した再生は持続可能ではない。再生を市場のメカニズムを使いながら、ソーシャルビジネスや金融等と連携し誰が(主体)どう進めていくのか。そのために必要な対応として法制度、政策なども含めた社会システムのあり方を考えたい。
『ネイバーフッドマネジメント』とは、あらたに設定した概念である。そこで、この言葉への思いを伝えたい。ネイバーフッドとは、近隣のエリア、地域や地区を指す概念で、かつ、ここには人だけでなく、暮らし、空間、その関係性、それを支える、慣習、ルールや文化、制度や仕組み等を含む概念である。従来のエリアマネジメント、コミュニティマネジメント、コミュニティディベロップメント等を包括する概念である。エリアマネジメントでは、地域を限定したマネジメントとなり、クローズドになってしまう。むしろ、エリアを限定せず、核を創り、その核から境界を越え、まわりに影響を与えていくような動きが必要ではないか。コミュニティマネジメントでは、コミュニティが主体となり、主体が限定的になってしまう。主体の多様性や連携がこれからの住宅地の再生に必要ではないか。コミュニティディベロップメントでは、開発がイメージされ、管理や再生が含まれない。そもそも、再生が必要になったのは、日常的な管理が適正に行われていなかった、あるいは、開発時から将来のことを考えた空間の作り方や、マネジメント体制が設定されていなかった可能性がある。そこで、開発、管理、建替え、改善などを総合的に考える必要がある。そうしたネイバーフッドをマネジメントしていこうというのが主旨(テーマ)である。
具体的には、郊外の戸建て住宅地の再生を含んだマネジメントのあり方、団地やマンションのマネジメント、両者を含んだまちのマネジメントなど、その実態と課題を明らかにし、あらたなマネジメント手法の確立と、そのための社会システムのありかたを考察していきたい。ゆえに、挑戦的な実践や、実践事例からのネイバーフッドマネジメントのあらたな手法確立を目指す研究を大いに応援したい。
研究テーマ設定のためのキーワード
- 郊外住宅地
- エリアマネジメント
- 住宅地再生・団地再生・マンション再生・まちの再生
- 公民連携(PPP、PFIなども含む)
- 市場活用・民間力活用
- ソーシャルビジネス・社会関係資本
- HOA・管理組合
「郊外住宅地のネイバーフッドマネジメント」研究委員会
(委員五十音順)
- 齊藤 広子
- (横浜市立大学 教授)
- 佐藤 元
- (横浜マリン法律事務所 弁護士/横浜市立大学大学院 客員准教授)
- 柴田 建
- (大分大学 准教授)
- 長谷川 洋
- (国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築研究部長)
- 藤井 さやか
- (筑波大学 准教授)
- 矢吹 剣一
- (東京大学先端科学技術研究センター 特任助教)
2023年度重点テーマ
「住まい造りの将来像」
蟹澤 宏剛(芝浦工業大学 教授)
重点テーマは、「住まい造りの将来像」である。住まい造りの技能者不足は深刻であり担い手の確保・育成は喫緊の課題であるが、新築と伝統技能を主眼とした技能者像、住まい手と造り手の関係などの観念を転換しなければ住まい造りの将来像は描けない。本テーマの趣旨は、住まい造りに関わる様々な視点での研究および、国内外の事例、胎動している新しい活動等々を調査・集積し、夢と希望のある住まい造りとその担い手の将来像を描くことにある。
日本の住まい造りを担ってきた技能者(職人)は減り続けている。特に木造住宅の中核を担う大工の減少は著しく、1980年のピークには90万人以上だったものが2015年の国勢調査では40万人まで減った。このままの勢いで減り続けると2030年代前半に20万人を割り込むことになる。高齢化も著しく、2020年では推定40%が60歳以上である。
担い手不足の要因は、賃金が低いこと、休日が少ないことなどにあるとされる。それは、技能者全般に共通することであるが、例えば大工に関しては、近年、急速に仕事内容が陳腐化してきたことが大きく影響していると考えられる。
かつて、大工は労働の付加価値も高く、棟梁は憧れの存在であったが今では仕上や建具の商品化が進んだことも相まって、大工は最終工程の取り付けを担うだけの存在になってしまった。
他方でDIYやセルフビルドが注目され、専門の情報誌やネット上の動画情報サイト、自由にDIYできることを売りにした賃貸物件なども増え、カリスマと称される「DIYer」も存在している。リノベーションを活用したコミュニティデザイン活動なども胎動している。しかし、それらに取り組む人々と技能者や建設業の側との隔たり、のみならず、業界内部における設計ともの造り、工務店等の組織と技能者の側との隔たりは小さくなく、課題や問題を共有できていないのが現状である。
この重点テーマでは、大工を中心とした住まい造りの担い手、技能者・職人に関する問題を整理すること、各地で胎動している住まい造りに関する新しい動きを拾い集めること、セルフビルドを始め国内外の様々な住まい造りの事例を収集すること、のみならず、従来隔たりの大きかったエンドユーザーと技能者、設計と実際のもの造り等々を繋ぐための実践的活動を皆様と共に試行しながら、住まい造りの楽しさややり甲斐と労働の付加価値向上を両立し、若者が憧れる新しい時代の住まい造りとその担い手の将来像を描きたい。
研究テーマ設定のためのキーワード
- 住まい手・住まい方
- リフォーム・リノベーション
- DIY・セルフビルド
- 大工・技能者・職人
- 技能・スキル
- 担い手の確保・育成
- 工務店・専門工事会社
「住まい造りの将来像」研究委員会
(委員五十音順)
- 蟹澤 宏剛
- (芝浦工業大学 教授)
- 河野 直
- (つみき設計施工社 代表)
- 権藤 智之
- (東京大学大学院 特任准教授)
- 佐々木 留美子
- (東北工業大学 講師)
- 角倉 英明
- (広島大学 准教授)
- 森田 芳朗
- (東京工芸大学 教授)
2022年度重点テーマ
多様化する住まい-環境価値の伝え方
秋元 孝之(芝浦工業大学 教授)
今回の重点テーマは「多様化する住まい-環境価値の伝え方」であるが「住まいの環境」はいろいろ考えられる。
「省エネ化・低炭素化」に関しては、パリ協定(COP21)において日本が提出した約束草案があり、CO2排出量を2030年までに2013年比で26%削減するという野心的な水準の目標が掲げられ、その実現のために、民生部門で2030年までに約4割削減することが求められ、住宅を含む建築物の省エネ化・低炭素化が推進されてきている。
分譲賃貸を問わず、戸建て住宅・集合住宅のZEH化は、良質なストックの形成の観点からも重要となる。中古住宅の改修においても地域の特性に合わせた断熱化、高気密化が推進されていくべきであろう。
改正建築物省エネ法による「建築士が建築主に対して行う省エネ技術の選択肢説明」の制度運用が開始される。その際には建築士が省エネ住宅ソムリエとして、光熱費削減等の効果のほか、高断熱化による健康・快適性の向上や、創蓄連携設備の導入による防災・減災性能の向上等といったコベネフィット(相乗便益)について、しっかりとわかりやすく紹介することが求められる。
建築士だけではなく、販売や仲介の不動産業者から環境価値やその便益の情報発信・伝達をすることが重要だが、今後はさらにその普及拡大を目指すために、意思決定者である建築主や入居を検討する人に正しく認知・理解されるよう教宣していく方法を探ることが不可欠である。海外における先進的な取り組みに関する現状調査・分析も必要である。
現在、日本ではBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)による住宅用途の評価書交付数は9万件を超えているが、住まい手への情報提供のボリュームとしてはまだ十分とは言えないし、不動産仲介の現場でも認知されることがまだ少ない。
住宅の室内環境には「空気質・換気」の問題や「光・音環境」「視環境」などがある。また、住戸間や外部の環境もあれば、まちレベルでの「住環境」もあり、いろいろな面からその生活環境価値を向上させる手法やステップが考えられる。いま、こうした情報をいかに一般の人々に伝えていくかが問われている。
現在、図らずも働き方改革が進みつつある。これを新たな働き方、生活の行動変容を読み解き、住まいやまちづくりのあり方を考える好機であると前向きに捉えたい。
今回の重点テーマでは、多様化する住まいの様々な環境価値を研究することによって議論を深めたい。
研究テーマ設定のためのキーワード
(参考例)
- 省エネルギー/ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
- 健康・快適性と住宅
- 環境情報の発信・伝達
- 住生活の行動変容
- 光熱費
- 高断熱・高気密
- 不動産情報
- まちづくりの環境向上
「住宅の省エネ化推進のための情報発信」研究委員会
(委員五十音順)
- 秋元 孝之
- (芝浦工業大学 教授)
- 池本 洋一
- ((株)リクルート SUUMO編集長)
- 齋藤 卓三
- ((一財)ベターリビング 認定・評価部長)
- 高口 洋人
- (早稲田大学 教授)
- 田辺 新一
- (早稲田大学 教授)
- 鶴崎 敬大
- ((株) 住環境計画研究所 取締役研究所長)
- 中村 美紀子
- ((株) 住環境計画研究所 主席研究員)
2021年度重点テーマ
「あこがれの住まいと暮らし」
後藤 治(工学院大学 教授)
いつの時代にも、人々があこがれる住まいや暮らしの形やイメージがある。その形やイメージ(以下では「あこがれ」という)は、住宅建築のなかに取り入れられ、その時代を特徴づける住宅建築の形をつくっている。
少し前、高度成長期の「あこがれ」には、「庭付き一戸建て」「nLDK」があった。最近では、「タワマン」「ヒルズ族」「田舎暮らし」といったところだろうか。「あこがれ」が形になって流布したものとしては、「玄関」「座敷」や「床の間」といったものがあげられるだろう。
「あこがれ」がつくりあげた形は、住宅の建築としての質的な向上に役立っているだろうか。住宅建築の質的な向上は、社会において重要な役割を果たす。エネルギー消費によるCO2削減は、その典型的なものだろう。最近の「あこがれ」は、住宅建築の質的向上に貢献しているだろうか。歴史上もすべての「あこがれ」が建築の質的向上に結び付いたとは言えないだろうが、質的向上につながったものがあったはずだ。
今回の重点テーマでは、かつての「あこがれ」と住宅建築との関係や、これからの建築の質的向上に結び付くような「あこがれ」の醸成について、様々な角度からの研究と実践を期待します。
研究テーマ設定のためのキーワード
(参考例)
- 和室の過去・現在・未来
- 建築家の住宅はあこがれになりうるのか
- 住環境・生活環境の国際比較
- 健康と住まい,幸福度と住まい
- 日常景観と都市居住のイメージ
- スマート化・センシングと生活空間
「あこがれの住まいと暮らし」研究委員会
(委員五十音順)
- 後藤 治
- (工学院大学 教授)
- 島原 万丈
- (株式会社LIFULL LIFULL HOME’S総研 所長)
- 豊田 啓介
- (noiz architects パートナー)
- 藤田 盟児
- (奈良女子大学 教授)
- 伏見 唯
- (株式会社伏見編集室 代表取締役)
- 山本 理奈
- (成城大学 准教授)