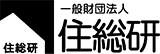第5回「住まい・まち学習」教育実践研修会 2018年3月21日(水・祝)
~住まい・まち学習のカリキュラム実践・デザイン力を磨く~
終了しました。
日時
2018年3月21日(水・祝)
13:00~17:00
13:00~17:00
参加
無料
定員
60名
締切
定員になり次第締め切り
主催
一般財団法人住総研「住まい・まち学習」普及委員会
後援
国土交通省
住総研「住まい・まち学習」普及委員会
委員長
・小澤紀美子 (東京学芸大学名誉教授)
委員
・勝田 映子 (帝京大学准教授)
・志村優子 (まちづくりプランナー)
・炭竃智 (教育図書株式会社)
・仙波圭子 (女子栄養大学教授)
・楚良浄 (世田谷区立玉川小学校指導教諭)
・中澤篤志 (国土交通省住宅局住宅政策課)
・小澤紀美子 (東京学芸大学名誉教授)
委員
・勝田 映子 (帝京大学准教授)
・志村優子 (まちづくりプランナー)
・炭竃智 (教育図書株式会社)
・仙波圭子 (女子栄養大学教授)
・楚良浄 (世田谷区立玉川小学校指導教諭)
・中澤篤志 (国土交通省住宅局住宅政策課)
プログラム
(1)講演
a. 委員会メンバーによる講演
小澤紀美子(東京学芸大学名誉教授)
勝田映子(帝京大学准教授)
楚良浄 (世田谷区立玉川小学校指導教諭)
b. 「住まい・まち学習」授業実践の発表
実際に住まい・まち学習に取り組む学校の先生方による事例、授業内容の発表。
(2)体験ワークショップ
希望のグループに分かれて、住まい・まち学習授業のワークショップを行います。
参加者同士の意見の交換や経験を通じて、授業づくりに生かせる体験ができます。
(1)室内の環境を「見える化」しよう!
室内の温度や湿度、音など目に「見えない」ものに関心をもつことが、快適な空間作りには欠かせません。そこで、サーモグラフィ・ソフト、湿度が見 える紙など「見える化」する方法例をいくつか体験します。そして、さらなる「見える化」アイディアを皆さんで考えていきます。
(2)協働生活スペースをつくろう!
災害で避難所生活をすることを想定し、スペースと人の関わりを考えます。実際に段ボールや机を使って生活スペースをつくり、協働生活を疑似体験し ます。防災訓練ではなく、教室という限られたスペースをどう活用すればプライバシーを確保しつつ便利に生活できるか、周囲の人々とコミュニケーショ ンをとりながら過ごせるかについて考えていきます。
(3)家族がみんなで集まる場を考えよう!
日本の住まいは家族のあり方と密接に関わって変遷しています。寛容さを失いつつある日本の社会において、情報の波に足元があやうく、さらに思春期 真っ只中で不安を抱えている中学生の居場所が見えづらくなっています。そこで家族と共に「ゆったり」と「心身ともにリラックス」し、家族の笑い声が響 き「居心地が良い」と感じる、明日のエネルギーを充実させる「家族みんなが集まる場」を考えます。
(4)多世代間交流空間を考えよう!(地域交流、居場所づくり)
人口減少の流れの中で、身近な学区の中で、あるいはまち全体として多世代交流・共生の視点に立った地域社会(コミュニティ)づくりが求められてい ます。団地の再生や交流カフェなど、いくつかの多世代間交流空間の事例をヒントにして、その担い手を育む授業づくりのアイデアを検討します。
a. 委員会メンバーによる講演
小澤紀美子(東京学芸大学名誉教授)
勝田映子(帝京大学准教授)
楚良浄 (世田谷区立玉川小学校指導教諭)
b. 「住まい・まち学習」授業実践の発表
実際に住まい・まち学習に取り組む学校の先生方による事例、授業内容の発表。
(2)体験ワークショップ
希望のグループに分かれて、住まい・まち学習授業のワークショップを行います。
参加者同士の意見の交換や経験を通じて、授業づくりに生かせる体験ができます。
(1)室内の環境を「見える化」しよう!
室内の温度や湿度、音など目に「見えない」ものに関心をもつことが、快適な空間作りには欠かせません。そこで、サーモグラフィ・ソフト、湿度が見 える紙など「見える化」する方法例をいくつか体験します。そして、さらなる「見える化」アイディアを皆さんで考えていきます。
(2)協働生活スペースをつくろう!
災害で避難所生活をすることを想定し、スペースと人の関わりを考えます。実際に段ボールや机を使って生活スペースをつくり、協働生活を疑似体験し ます。防災訓練ではなく、教室という限られたスペースをどう活用すればプライバシーを確保しつつ便利に生活できるか、周囲の人々とコミュニケーショ ンをとりながら過ごせるかについて考えていきます。
(3)家族がみんなで集まる場を考えよう!
日本の住まいは家族のあり方と密接に関わって変遷しています。寛容さを失いつつある日本の社会において、情報の波に足元があやうく、さらに思春期 真っ只中で不安を抱えている中学生の居場所が見えづらくなっています。そこで家族と共に「ゆったり」と「心身ともにリラックス」し、家族の笑い声が響 き「居心地が良い」と感じる、明日のエネルギーを充実させる「家族みんなが集まる場」を考えます。
(4)多世代間交流空間を考えよう!(地域交流、居場所づくり)
人口減少の流れの中で、身近な学区の中で、あるいはまち全体として多世代交流・共生の視点に立った地域社会(コミュニティ)づくりが求められてい ます。団地の再生や交流カフェなど、いくつかの多世代間交流空間の事例をヒントにして、その担い手を育む授業づくりのアイデアを検討します。
会場
東海大学 高輪キャンパス 4号館2階 4201・4203 教室
会場MAP