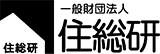第103回すまいろんシンポジウム 2025年3月11日(火)14:00~17:00
「和室」のこし方ゆく先/これからの「和室」のはなしをしよう 終了しました。
「和室」が消滅の危機に瀕している。「和室」を設ける新築住宅の数は減り、既存住宅のリノベーションでは「和室」を無くす傾向にあることが指摘される。茶道や華道をはじめとする伝統文化の場として、あるいはホテルや旅館が日本らしいくつろぎを演出するための選択肢として、「和室」はかろうじてその命脈を保っている。つまり、「和室」は多くの日本人にとってもはや日常にはなく、日本らしさのアイコン、非日常の空間として意識的に体験するものとなっている。果たして、それでよいのだろうか。
そもそも「和室」とは何か。その定義は簡単ではない。ひとまず畳が敷き詰められ、襖や障子などの引き違い建具で囲まれた室とするならば、その誕生は中世の武家住宅に遡る。そして「和室」という言葉は、明治以降、この国の住宅に「洋室」が受容される過程で、「洋室」に相対する概念として立ち現れた。「和室」という言葉の出現は、伝統的な住まいを相対化する視座の獲得を意味すると同時に、伝統的な住まいに対する認識の布置そのものを変える契機となることで、現在に至るこの国の住まいの変容の出発点となったといえる。
「和室」を考えることは、われわれの住まいと暮らしを考えることにほかならない。われわれの生活習慣(たとえば靴を脱いで家に上る、床に直接座る・寝転ぶといった振る舞い)、伝統文化との関係、開放的な間取り、屋外(自然)との高い親和性、建築のモジュール、伝統的な建築材料と技術など、この国の住まいと住まうことの本質的なあり様は「和室」のなかにある。「和室」が消えていく理由はさまざまある。しかし、この国固有の生活空間である「和室」がこのまま消えて良いとは思えない。
「和室」はどこから来て、どこに向かうのか。いま「和室」を再考し、その可能性を語ることは、われわれの住まいの未来のために、必要な作業であり、起こすべき新たな潮流であると考える。本シンポジウムでは、伝統建築や大工仕事に向かい合う若手の作り手とともに、これからの「和室」のはなしをしたい。
企画:中嶋 節子(京都大学大学院 教授/すまいろん企画編集委員会委員)
第103回すまいろんシンポジウム 「和室」のこし方ゆく先/これからの「和室」のはなしをしよう
14:00~17:00
「和室」のこし方ゆく先/これからの「和室」のはなしをしよう
「大工仕事と和室」
田野倉 徹也(田野倉建築事務所)
「伝統建築をつくることから見える「和室」の現在地と可能性」
内田 利惠子(建築設計室Morizo-)
「海外における「和室」の受容と実践」
※講演者、講演タイトル等は変更になる場合がございます。
e-mail sumairon★jusoken.or.jp (★は@(半角)に変えて下さい。)
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング2階
TEL:03-3275-3078/FAX:03-3275-3079
このシンポジウムの内容は、2025年8月発行予定の『すまいろん』(No.117)に掲載予定です。