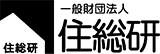第88回すまいろんシンポジウム 2017年10月2日(月)14:00~17:00
『「立地適正化」の先のすまい』 終了しました
2014年、都市再生特別措置法において「立地適正化計画」の制度が創設された。これは強い居住誘導策に、集約的な「地域公共交通網」の形成を組み合わせようとするもので、平成28年12月の国交省の調べでは全国で308の自治体が具体的な取組をしているとされている。立地適正化計画における居住誘導の特徴は、将来的にも一定の人口密度を期待できる「居住誘導区域」を都市計画区域内に限って定め、福祉や商業などの「都市機能誘導区域」をその区域内に限って定めることができる、という手法である。いよいよ人口縮小社会が、スプロール抑制から計画的な縮小にフェーズを移しつつあることを表す政策である。 キーワードとして重みを増す「居住誘導」であるが、実際にどのような住まいに誘導するのか、そのイメージは明確ではない。北原*は青森市の中心市街マンション居住者のアンケートで「余暇を楽しむ施設や機会」「医療福祉施設の充実」「中心市街地の魅力」への満足度が30%ほどしかなかったという結果を踏まえ、「まちなか居住」の実態が理想に追いついていない状況を紹介している。また、小林**は敷地面積が160㎡程度の郊外居住地は市街地居住と決定的な差がなく、その維持には面積増などの魅力創出が必要であると述べている。 住まい方のイメージが明確ではない、というのは福島県矢吹町の復興まちづくり計画に関わった担当委員の実感でもある。都市域の縮小を見据えなくてはならない人口1.8万人の町で、不明瞭だったのは①まちなか居住のライフスタイル、②高齢化が進んだ後の郊外居住の交通計画、③それらを見据えた地域公共交通形成および縮小の誘導の方向性であった。その1つの要因は、商業の衰退により宅地化してしまった中心市街地と市域外での郊外居住の間に顕著な差がなく、まちなかに住み替える動機が少ないことにある。これらは地方都市およびその都市圏において共通の課題であると考える。 すまいろん102号では、立地適正化計画が対峙する縮小の現実の先に、まちなか、郊外の新しい居住ビジョンを描くことが可能かについて、実例の収集・分析を行いつつ議論する。まちなか居住と自動車利用、郊外居住と公共交通網形成の具体的な進捗など、交通と居住の関係には特に注意を払うものとする。
企画:太田浩史(一級建築士事務所ヌーブ 代表取締役、住総研すまいろん編集委員)
*コンパクトシティにおける郊外居住の持続可能性とは,「すまいろん2012」北原啓司, 2012
**都市と家族の縮小を住まいの豊かさに転換する,「すまいろん2012」小林秀樹, 2012
主催:一般財団法人 住総研
第88回すまいろんシンポジウム 『「立地適正化」の先のすまい』
14:00~17:00
吉田 樹(福島大学 准教授・人文社会学)「地域公共交通とまちづくり」
乾久美子(乾久美子建築設計事務所 主宰・建築家)「これからの地域と居住」
※講演者等は変更になる場合がございます。
e-mail sumairon★jusoken.or.jp (★は@(半角)に変えて下さい。)
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング2階
TEL:03-3275-3078 / FAX:03-3275-3079
このシンポジウムの内容は、2018年2月発行予定の『すまいろん』(No.102)に掲載予定です。
会場
〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目12番2号朝日ビルヂング2階
一般財団法人 住総研 事務所内会議室
http://www.jusoken.or.jp/gaiyou/way.html